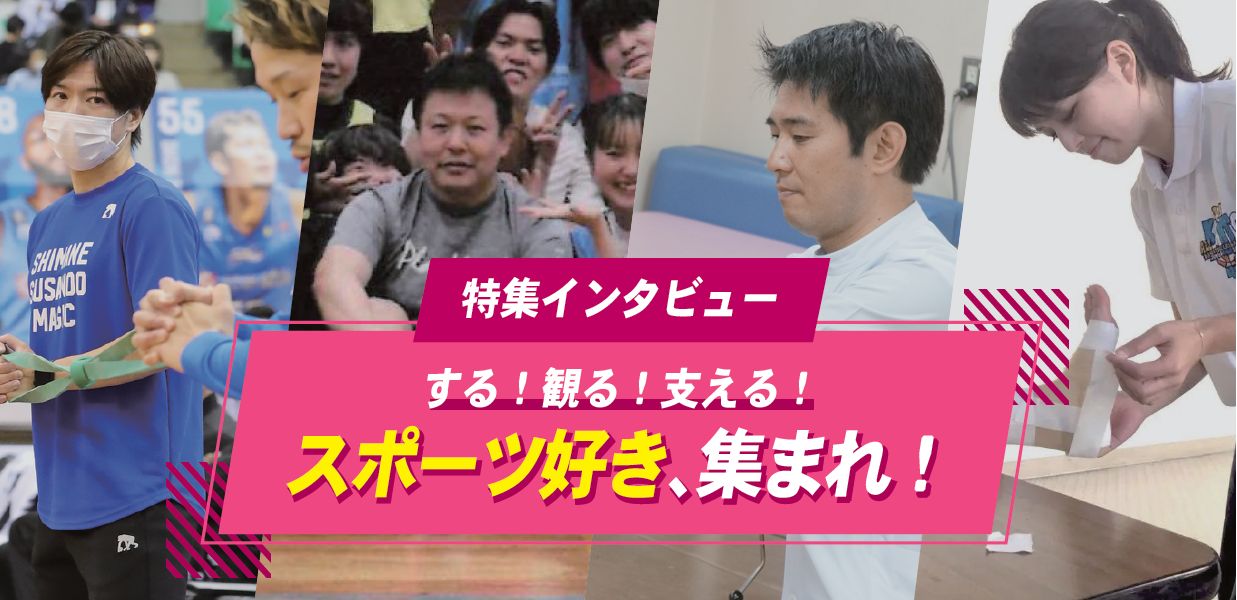©SHIMANE SUSANOO MAGIC
眞田 崇 さん
B.LEAGUE 島根スサノオマジック 理学療法士兼アシスタントストレングスコーチ
2012ロンドンパラリンピック 車椅子バスケットボール競技 日本代表トレーナー
東都リハビリテーション学院 1部10期生 卒業
結果も大切、だからこそプロセス(=過程)を意識すること。常に修正や評価を行い、課題をもって前向きに取り組もう。
私は高校1年の頃、所属していたバスケットボール部の練習中に怪我で膝前十字靭帯を損傷してしまいました。手術は
栗山節郎先生に、リハビリは
川島敏生先生(当時は日本鋼管病院所属、現在は本校専任講師)にご担当いただきました。約1年間、競技出来ずにリハビリに取り組みましたが、膝の治療だけではなく、常に励まされて前向きにしてくださる先生方に感激し、私自身も理学療法士を目指すことを決めました。
現在は、プロバスケットボールチームBリーグ「島根スサノオマジック」にて理学療法士兼アシスタントストレングスコーチとして従事しています。私の役割は、チーム全体のウォーミングアップやエクササイズ、ストレッチ、ウエイトトレーニングなどを指導しています。ウォーミングアップでは、心拍数を上げた状態で練習にのぞめるようなメニューを組んだり、バスケットボールで多い動き(例えば、ジャンプから着地の動きや切り返す動き等)なども重点的に指導しています。また、全体だけではなく、膝を怪我している選手や腰痛を起こしやすい選手などは個別にその状況に配慮したメニューを行っています。指導している中で選手個々の状況を確認し、「今日は動きが軽やかだな」などと日々の細かい変化やコンディションを常に観察することに努めています。
ウェイトトレーニングが週2回、1人3~40分実施しており、選手によって、ポジションによって、また選手の怪我等の状況によって内容を変える等を工夫しています。
選手はプレイタイム(試合に出ている時間)が命です。活躍できなければ次のシーズンの契約にも影響が生じることもあります。チームの成績はもちろんですが、選手個々でも試合で活躍している状況もあれば、うまくいかない状況もあります。そのため、常に選手とコミュニケーションを多くとり、コンディションの状況を知ることを心がけています。
怪我する前よりもコンディションが更に良い状態に高めることを目標に。現在、年間60試合の公式戦があり、月に6~10試合と流動的であるため、スケジューリングがとても重要です。例えば、練習の強度もコーチと十分に相談しながら「今日は軽め」「いつも通り」などと意思疎通を図り、先のスケジュールを見据えながら練習の強度を見ています。チームや選手の状態は日々変化しています。選手の身体を診るだけではなくチーム全体を見渡すことが大切だと思います。選手が怪我をした場合、ドクターの診断で「全治3か月」等と診断を受けます。状況にもより、決して無理して戻すわけではありませんが、競技復帰することが求められます。怪我する前よりもコンディションが更に良い状態に高めることを目標に、日々取り組んでいます。
2022-2023シーズン、チームはBリーグ内で勝率が高い結果でした。しかし、勝っても負けても、コーチやトレーナーのみならず選手自身からも自発的に修正点や改善点を出し合って、常にチームの状況を良い方向に導いていく全体の雰囲気がありました。これはプロスポーツ現場のみならず、どのような現場でも大切なことだと学びました。「プロは結果が大切」ですが、良いプロセス(過程)がないと、良い結果が出ません。「勝ったから良い」「負けたからダメ」と結果ばかりを追い求めるのではなく、1日1日、課題をもって取り組み、プロセスを振り返って、修正したり評価したりを繰り返すことが大切だと思います。

©SHIMANE SUSANOO MAGIC
自分の可能性を信じて挑戦しよう。勇気をもって自分から一歩踏み出そう。自分の夢を実現させるためには、可能性が1%でもあればあきらめず、そして常に謙虚で素直に行動してみましょう。対価のみならず、経験や人のつながりが大切な財産となります。自分に可能性はないのかな、無理なのかなと思わず、自分の可能性を信じて挑戦してほしいと思います。
東都リハビリテーション学院は、私の場合、クラスメイトに”スポーツで怪我して理学療法士になりたい”と同じ志を持つ仲間が多く、みんなで将来の話をする機会が多くありました。また、学校行事が多いので、授業ばかりではなく、定期的に息抜きやクラスメイトとの親睦が深められるような雰囲気がとても良かったです。先生や仲間に相談することで自然とモチベーションが高まります。自分がやりたいことは、勇気をもって自分から一歩踏み出すことが大切だと思います。頑張ってください!
Profile私立日本学園高校を卒業後、本校アスレティックトレーナー学科に入学。卒業と同時に本校理学療法学科に入学し、在学中から車椅子バスケットボール「千葉トマホークス」でトレーナー活動を行う。本校を卒業し、理学療法士国家資格を取得、整形外科に勤務しながら、バスケットボールに限らず、様々な競技のアスリートのコンディションサポートを行う。2010~2016年、車椅子バスケットボール日本代表のトレーナーに選任、2012年ロンドンパラリンピック、2014年世界選手権、2016年リオパラリンピックアジア予選に帯同。2019年にBリーグ島根スサノオマジックにて理学療法士として、2020年より宇都宮ブレックスにストレングスコーチ 兼 ヘッドトレーナーとして、2022年より島根スサノオマジックにて理学療法士兼アシスタントストレングスコーチとして活躍している。